
瀬戸内海を展望できる小高い丘を開墾し、築窯して以来絶えることなく窯の火が燃え続けています。
開窯からの歴史
開窯からの歴史に基づいた写真です。いずれも撮影された方の許可を得ています。

この写真は昭和10年皿山の海水浴場を撮影した写真である。大津野湾の海岸は水質も大変きれいだったので海水浴場や別荘地としてよく使われていた。
海水浴にきていた中学校、今の高等学校にあたる女子生徒たちの写真で水泳前の体操風景。
後ろの山の白く映っているところは、粘土として山土を採取した跡.登り窯で大物を焼いていたので大量の粘土を必要としていた。その結果かなりの山土を採取したようだ。
陶津窯についての記事の紹介(古い文献から)
村上正名著(備後のやきものから)
陶津窯について (原文のまま)
梅の花がほころびて、眼下には大門湾の海が青い波をただよわせていました。陶津翁はとつとつと語りつがれてゆきます。
八十幾歳の高齢でなお陶車に向かい、「明るさび」とでもいうか白釉の美しい釉に姿をつつむ茶器に、みどりあわだつ茶をすすりつつ私は陶芸にうちこまれた一生の物語を聞いていました。
明治八年十二月の生まれといえば、明治百年のほとんどを生きぬかれたわけです。しかもそれは陶技一筋の歩みなのです。
藩の貢皿山として、国産奨励の波にのって誕生した岩谷焼、明治の御変革によって藩との関係が絶えて、民間の経営となった窯は、その後転々と窯主をかえ、陶工が独立しての長崎窯や、大わだ窯、古屋窯が生まれますが、いずれも伊万里物や瀬戸物の大量生産におわれて、ほそぼそと煙をあげていたのです。
陶津翁はこうした岩谷の陶郷に成長して、陶工としての腕をみがいていったのです。今の吉備焼の前身、山陽陶器株式会社として大門湾をはさんでめとはなの岡山県側の城見損の浜辺に、この人を棟梁として窯が築かれたのは明治39年でした。
30歳をわずかに出た陶津氏の張り切った仕事場がうまれたわけです。
そして40歳も半ばに達する大正8年はじめて、自分の経営する窯を現在の地に築いたときの陶津氏の喜びはこの上もないものでした。しかし制作と販売経営の道はまことにいばらの道でした。
とつとつと語られる翁の陶談、現在のようにテープレコーダーが発達していれば、この物語を採録しておけば明治、大正、昭和を陶芸一筋に生き抜かれた陶工物語の一遍が綴られたものと、残念でたまりません。

開窯当時、初代陶津
かつて戦後福山で戦後復興の博覧会を計画し、その一端として久松城の伏見櫓で美術展を開催したとき、会場の陶津翁の茶碗が盗まれた事件がありました。
会場の係は度を失ってこまりはてていますと、翁は「私はこんなにうれしいことはございません。私のものでも盗むほどですから、よっぽどほしかったのでしょう。
そんなに罪をおかしての私のやきものを愛していただけるなんて、焼き物師のみょうりにつきます。」とかたられたのを思い出します。
父は一生私の家ではわらじをはいていました。しかもそれは父が手づくりなんです。いつも閑なときわらを打ってきれいに作って、工房ではこのぞうりをはいて仕事をしていました。令息肇氏の父思いは、窯の名も陶津窯と名つけての孝心ぶりがうかがえます。
「あんなやさしい日頃の父でしたが、陶技についてはとても厳しい父でした。
そうでしょう、二、三年もすれば作家でござると通用さす現在の陶芸界で、ロクロの腕、土をこなし、窯をたく技術のすばらしさ、数十年を陶工としてたたきあげられた労苦はなみなみならぬものです。
その陶津翁が九十二歳の天寿をまっとうして他界されたのはつい最近です。
晩年は令息肇氏の成功を見守りつつ中国文化賞の受賞、かずかずの展覧会に招待作家として入選、入賞もかぎりなき栄誉をにないつつ、作陶に精進されていました。
令息肇氏が日展常連として、又昭和42年度日展には作品「耐」が特選となり、北斗賞が受賞され、昭和43年度以来無鑑査出品となり、県展審査員、現代工芸中国部会副会長など第一線に活躍し、その作品が各種展覧会に入賞かぎりなく、日本の現代陶芸の代表的存在なのです。
初代陶津ロクロ座にて制作中

それにうれしいことに、孫の明成君まで、東京芸大に学び父親の道を継いで陶芸に精進し、大学院陶芸専攻科を卒業して、父のもとで技を練磨しているのです。かくて父より子、孫へと三代の道は拓かれつつあります。
今は海もうめられ、眼前には臨海工業地帯がひろがり、備後工特区の要である日本鋼管福山製鉄所がひろがっています。しかし、この山すその一角にはもくもくと陶芸に生きる一家の窯が一筋の煙をたやしていないのです。
以上
仕事の後一服

当時のアトリエから瀬戸内海を望む
雪景色で、当時は海水も凍り波の音は、あたかもガラスが 打ち付けられるようだったという

海岸は子供たちの遊び場だった。ダベにシャコや貝の穴が開いていて、岩の下にカニが潜む様子は今でも鮮明におぼえている。
特に印象深かったのは、カブトガニで、小さいものから大きなもの迄、並べてよく遊んだ。脱皮をよくするので腐敗した皮の匂いが強かった。
あのかわいいカブトガニが埋め立てで全滅、しかも生き埋め状態だったと思うと、なんとも……。
既に思い出の地は工業地帯につながる道路の下になってしまっている。

写真の大津野湾は、明治五年に築かれた堤防によって田園地帯と区切られている。
その堤防を撮影した写真の古いネガがみつかったので写真にしてみた。
山のふもとにあった小・中学校までの通学路は片道2キロ。
中学校卒業までの9年間を歩いて通学した。
大雨のときなど道路はすべて水没し、道の上でフナが泳いでいたし、メダカやカエルを雨靴でかき分けながら通学した。
又山沿いの細い道は山崩れで埋まってしまい海に出て船で迂回などしていた。
(太平洋戦争中のことがらを中心として) 初代陶津の一寸変わった作品を紹介します。

庭園の飾り ヒキ
このヒキカエルには、右手が先で這う、座る、左手が先で這うの三種類あり現在写真のものしか確認できていない。(所有されている方がおられましたらメールを)
中は空洞になっていて、部分ごとにつくってはりあわせた。焼くときもひずまないように支えて窯で焼いた。
二宮尊徳像
 二宮金次郎の勤勉さを戦時中教育のシンボル化として作られた。
二宮金次郎の勤勉さを戦時中教育のシンボル化として作られた。
陶器の像の他に木製、セメント、等ある。像本体は初代の作。
背の薪の部分は二代の手で創られた。
二宮尊徳像除幕式 ○○小学校

このスタチュウは現在も、ある小学校に立っている。
戦前の子供たちを見守り、又空襲にも耐え、戦後の荒廃と高度成長を経て、時代の変革期を迎えている今日、尊徳さんの勤勉さに学ぶことも多いかもしれない。
開窯から数年後の1941年12月、太平洋戦争が勃発。戦時下において制作する作品が変化してきたことが上の写真から窺がえる。
水閘(すいこう)
水閘について二代陶津の説明(原文のまま)
 『暗渠排水の部分で「水閘」と云ふ。
『暗渠排水の部分で「水閘」と云ふ。
農林省の土地の改良目的で作られた。湿田に埋め込み、排水をうながし田を耕地に適した土地にして、食糧増産の道具となった。
窯を焼く燃料も不足する時代であったが、作ると窯の燃料を三回分くれた。
登り窯で900個焼いて渡したが、事変も終わり戦争に負け不必要になり後の製造はなし。』
松根油用冷却器

松根油用冷却器についての説明(原文のまま)
『松根油、不足する航空燃料に加えるため、戦時中各地の松の根を掘った。
肥えた松を焚いて油を搾り出し、それを冷却するための装置。
上部の大きな穴から下の排出口にゆっくり流れて出るまでに冷却される構造であった。
複雑な形を山土で作って、登り窯でやきあげた。この形につくる過程を次回説明します。
試作が出来上がった段階で戦争終了となり利用されたかどうか不明。
その他変わったモノとしては手榴弾がある。
太平洋戦争前のことがらを中心として

白い桃の花の咲く春のひと時。
窯だし後、気に入った作品を選別し感慨にひたる。もの作りにとってなんともいえぬ瞬間である。

この写真も同じ頃。
背景の大津野湾は瀬戸内海の湾のひとつ。
現在は工業地帯になってしまっている。
垣根も植物のカヤの茎で作ってあり、風を防ぎ乾燥の調整に使っていた。カヤの微妙な隙間がその調整弁であった。
体力のあった頃の初代の作陶風景。

当時のロクロは電動ではなく足で蹴って回転させていた。
成形の時は左足で内側に蹴って左回転を使い、削り仕上げの時は右足を使用しての右回転であった。
当時の作品の高台をみるとその特徴がよくわかる。高台は作者の実力があらわになる最も怖い場所。
初代75歳頃の作陶風景
乾燥風景
 当時の粘土は山から採取した赤土を精製して使っていたので、作品の乾燥には最大の注意を払わなければならなかった。
当時の粘土は山から採取した赤土を精製して使っていたので、作品の乾燥には最大の注意を払わなければならなかった。
制作上の技術と削り仕上げの調整に加味して、風、温度など自然環境の要素も肌で感じながら乾燥に注意を払っていたと思う。
粘土濾過場
山から採取した材料を濾過する作業所。
 手伝っていただいていた人のひとり。攪拌棒をもってのひとこま。
手伝っていただいていた人のひとり。攪拌棒をもってのひとこま。
そういえばこの池に落ちたことがあったのを覚えている。水中からみた空のライトブルーは印象的だった。
ひたすら制作
 蹴りロクロの回転するシン棒の先と盤の回転の接触面には陶器製の皿がセットされていた。
蹴りロクロの回転するシン棒の先と盤の回転の接触面には陶器製の皿がセットされていた。
現代のロクロはベアリングを使用している。
回転の微妙な不正確さがかえって茶道具などにいわゆるアジをもたらせたかもしれない。
形が出来上がった後窯にいれ焼成過程にはいる
登り窯
 この窯も手製
この窯も手製
窯をつくるにはトンバリと名づけられたレンガを使用する。そのレンガも当然自分で作らなければならなかった。
材料も山から採取することになり、作品とちがって窯壁の粘土は耐火度も必要なので山土の採取にあたっても最適な土を選別する眼力が必要であったろう。
この登り窯でトンバリが約15000個必要であった。
登り窯の断面図
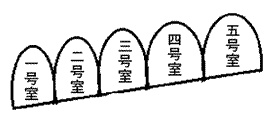 左の部屋から火がのぼっていき右側から排出され、熱効率を最大限に利用した構造になっている。
左の部屋から火がのぼっていき右側から排出され、熱効率を最大限に利用した構造になっている。
大作の焼成には必需品であった。このような窯も売っているわけではないので当然自作が必要となる。
登り窯の焼成風景
 窯の火をいれて焼きあがるまで、約50時間必要なので15人の助け人をお願いして昼夜を分かたず窯焼成の作業をした。
窯の火をいれて焼きあがるまで、約50時間必要なので15人の助け人をお願いして昼夜を分かたず窯焼成の作業をした。
完成品の出荷風景
 大作が多かったので藁をまいて破損を防いだようだ。
大作が多かったので藁をまいて破損を防いだようだ。
このような梱包のやり方は現代では無理かもしれない。
窯内の色の変化を微妙に感じ取って薪の投入を決断するこのタイミングの判断は大変だけど面白い。
薪の運搬

 下の海岸から人力ですべての物資を運び込んだ。窯一回の焼成に約三千束の薪が必要だったようで、この約100メートルの坂が数々の思い出を残すことになったようだ。
下の海岸から人力ですべての物資を運び込んだ。窯一回の焼成に約三千束の薪が必要だったようで、この約100メートルの坂が数々の思い出を残すことになったようだ。
完成した甕などもこの坂を運び下ろしていた。
完成品
 この当時の釉薬は融点の許容範囲が狭くしかも薪窯で温度制御が困難な構造の窯の為、製品の完成%は非常に低かったと想像できる。
この当時の釉薬は融点の許容範囲が狭くしかも薪窯で温度制御が困難な構造の窯の為、製品の完成%は非常に低かったと想像できる。
不完全な焼成によって思いがけない発色が得られたこともあるだろうが現代にあっては珍しい色も全て再現は簡単に可能であるので、窯の焼きの偶然性に依存した作品は意味をもたない。
陶津窯伝統の白釉薬

この写真の作品にかかっている釉薬は初代が苦心の末あみだした「白釉」でいまでも陶津窯の代表的な上釉薬となっていて、調合は企業秘密となっている。この白釉と赤絵が物理的にマッチングが悪いので今研究しているところ。
大作の写真
 輸送手段の発達によって良質の粘土が簡単に手に入る現代では、写真のような大作も、なま掛けで制作することができるが、当時のように山土を使用して完成させるパワーが現代人にあるかどうかは疑問である。
輸送手段の発達によって良質の粘土が簡単に手に入る現代では、写真のような大作も、なま掛けで制作することができるが、当時のように山土を使用して完成させるパワーが現代人にあるかどうかは疑問である。
初代陶津の代表的な作品として献上品の制作がある


当時献上品の制作をまかされることは大変名誉なことで、白いのぼりには〔献上品制作工場〕とある。
白い服にきかえて精神統一をはかり制作に取り掛かったときいている。


